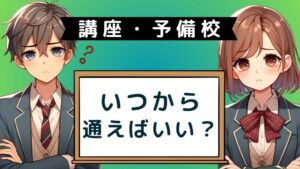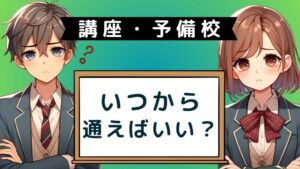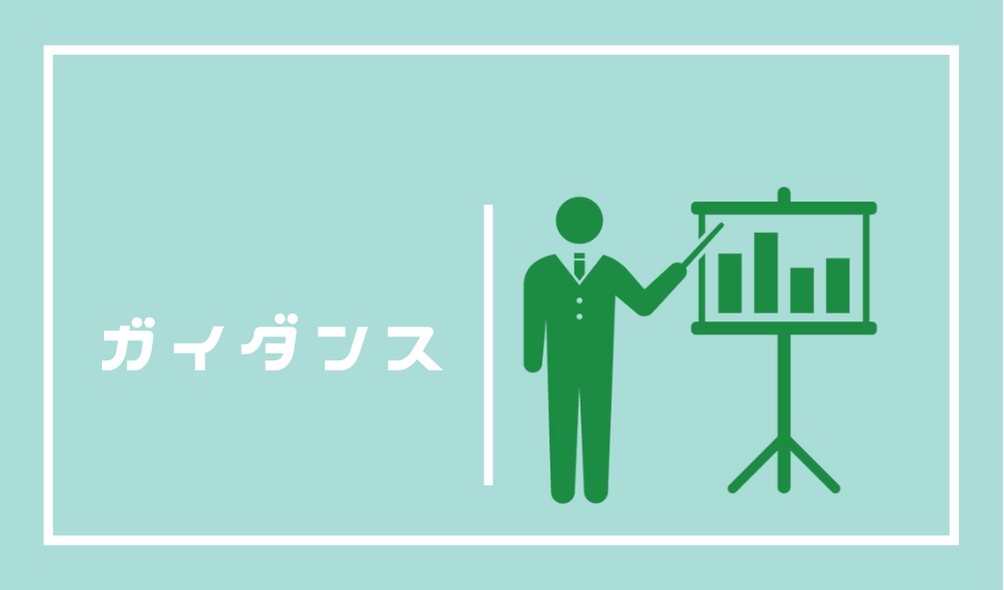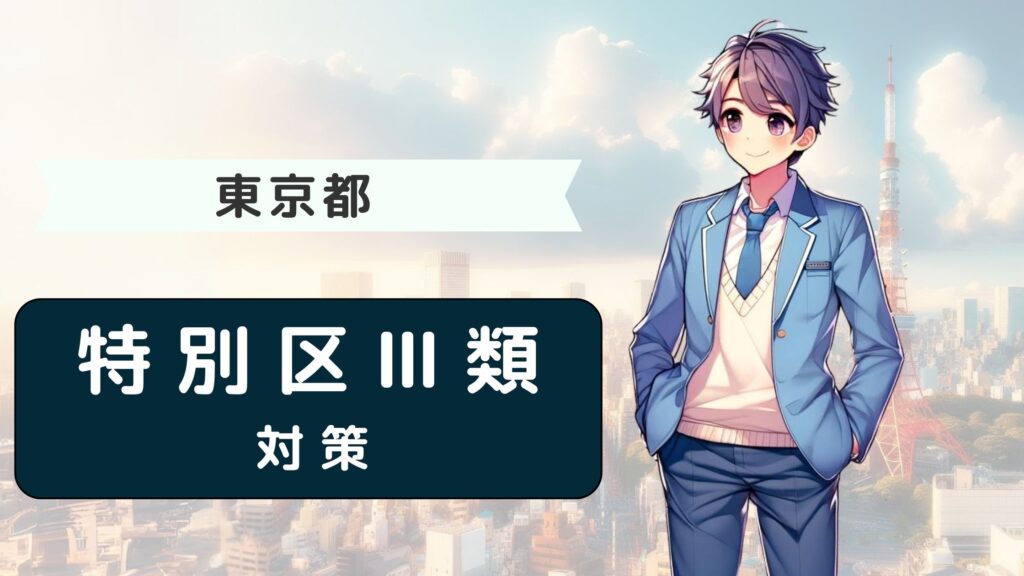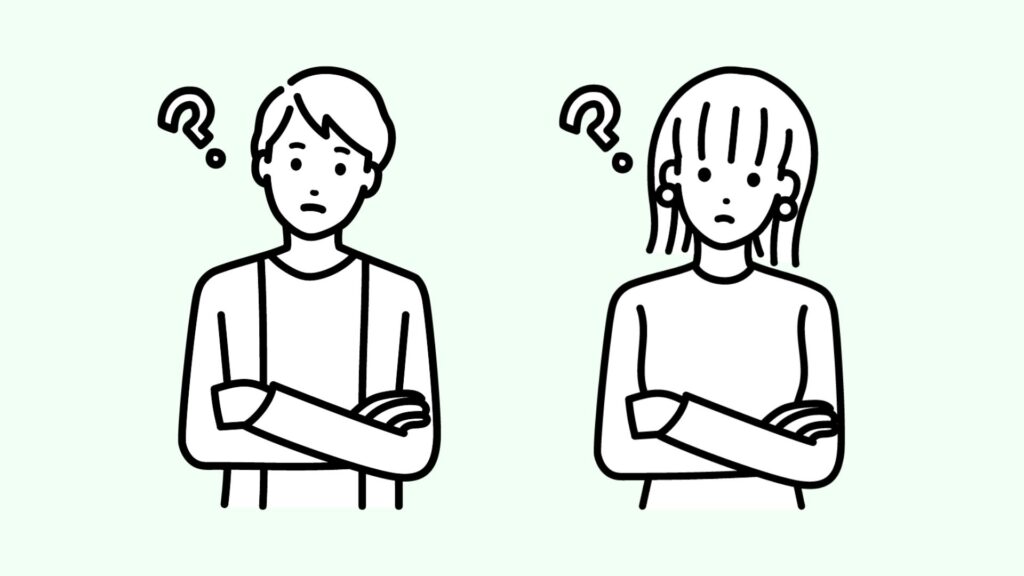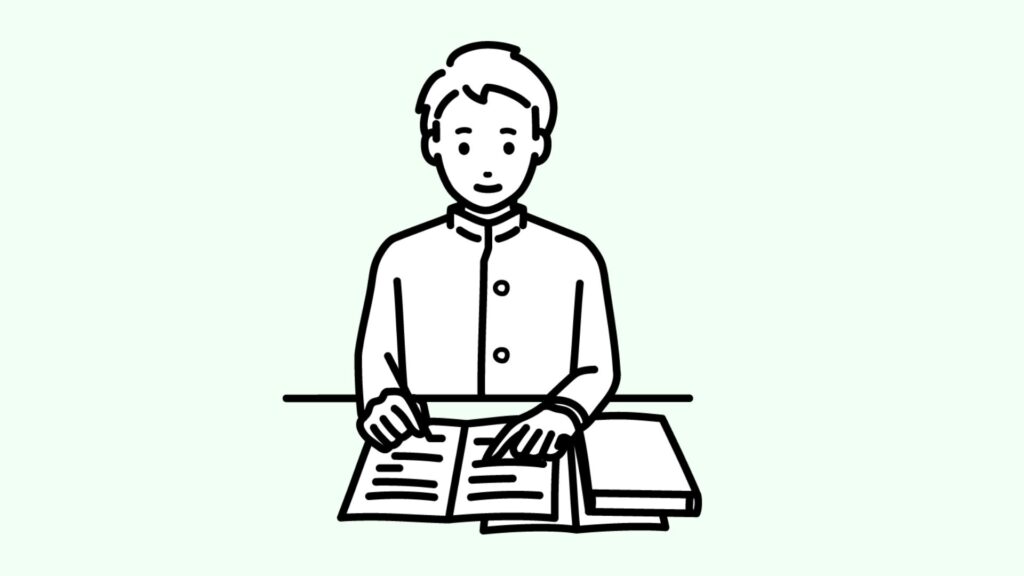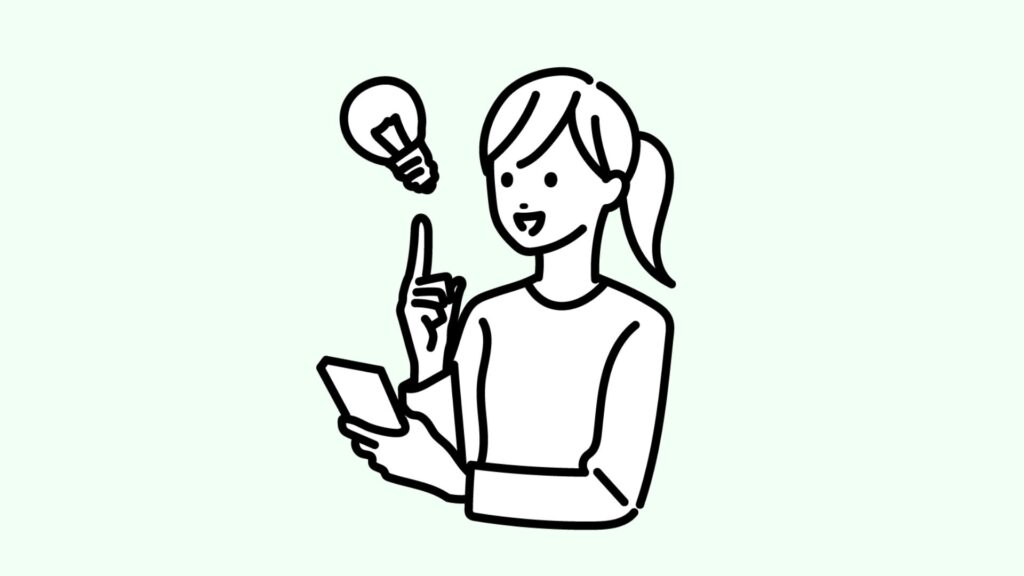東京都特別区Ⅲ類の試験は、高卒公務員試験の中ではかなり特色があります。
対策には、試験の特徴を押さえておくことが必須。
特色を押さえておかないと、大失敗することもあります。

高卒公務員指導歴10年以上、元・専門学校公務員科教員の僕が東京都特別区Ⅲ類の特徴について解説します!
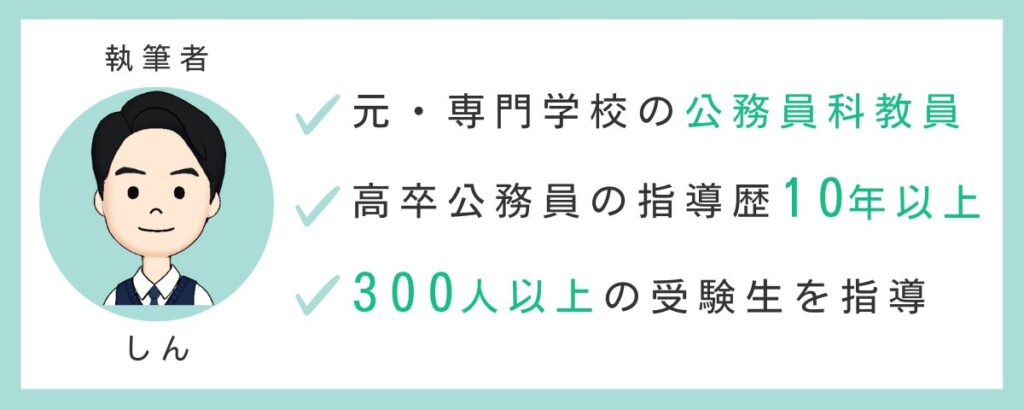
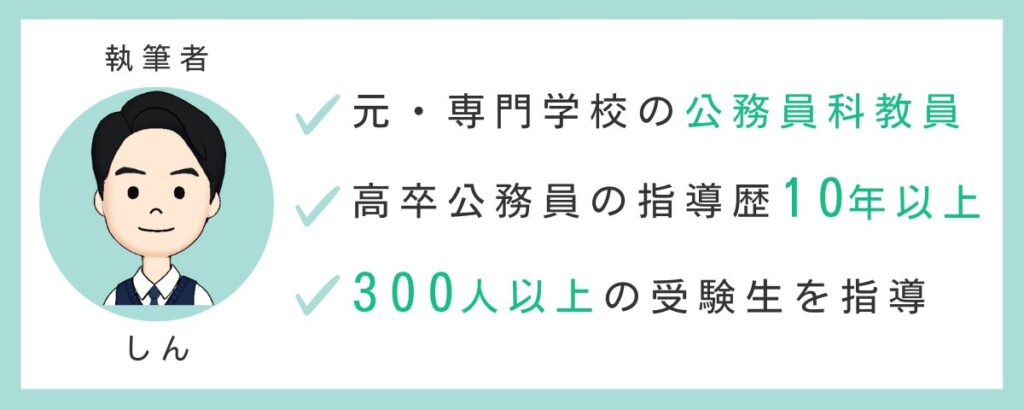
X(Twitter)しん@元・専門学校の公務員科教員
\ 高卒の対策講座があるのはこの9つ/
  |   |   |   | ||||||
| 価格 | 150,000円 | 約165,000円~ | 376,475円~ | 118,000円 | 84,000円~353,500円 | 148,000円 | 35,200円 | 199,600円 | 127,300円 |
| 割引 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 受講 | 通信 | 通学 | 通信・通学 | 通信 | 通信・通学 | 通信 | 通信 | 通信・通学 | 通信 |
| 警察官・消防官コース | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 作文対策 | 有 添削回数無制限 | 有 回数無制限 | 有 | 有 1人3通 | 有 | 有 添削3回 | 有 添削2回 | 有 | 有 添削1回 |
| 模擬面接 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 有 | 有 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 無 | 有 | 有 回数無制限 |
| 特徴 | 充実のカリキュラム!通信ならここがおススメ! | 担任の面倒見が良い予備校。高い合格率も魅力 | 二次試験対策にこだわったスクール | 価格で選ぶならアガルート。今なら10%OFF! | 大手ならではの情報量と分析で受験生をサポート | 万全の面接対策で独学では不可能な部分もカバー | 動画ではなく、テキストを自習するスタイル | 全国展開の専門学校で有名な大原グループが運営 | 無料で1年間の学習期間の延長サービスがある |
| 公式 サイト | クレアール | EYE | アガルート | 東京アカデミー | LEC
| 実務教育出版 | 資格の大原 | Human
| |
| 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求
| ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 |
解答時間は2時間
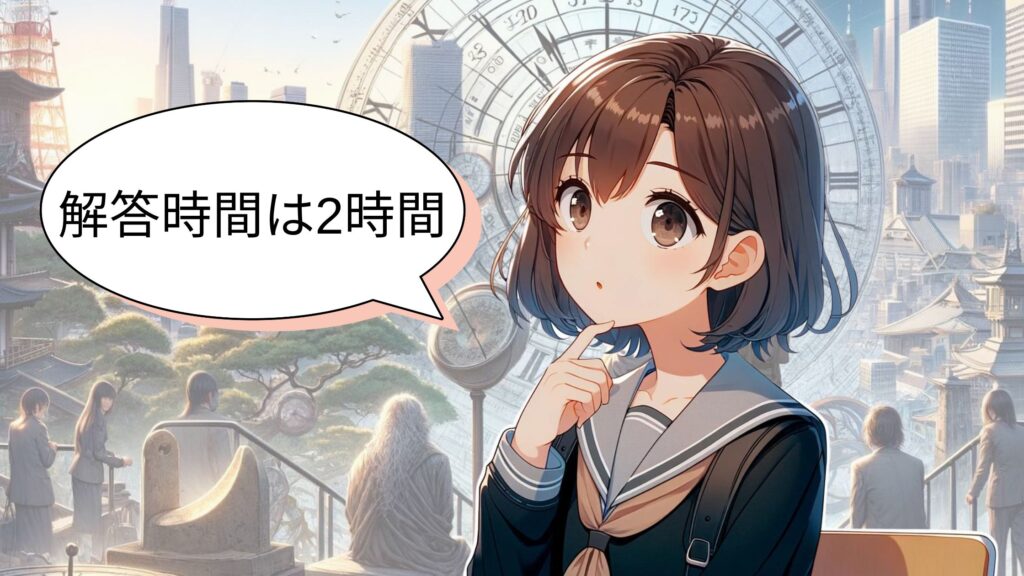
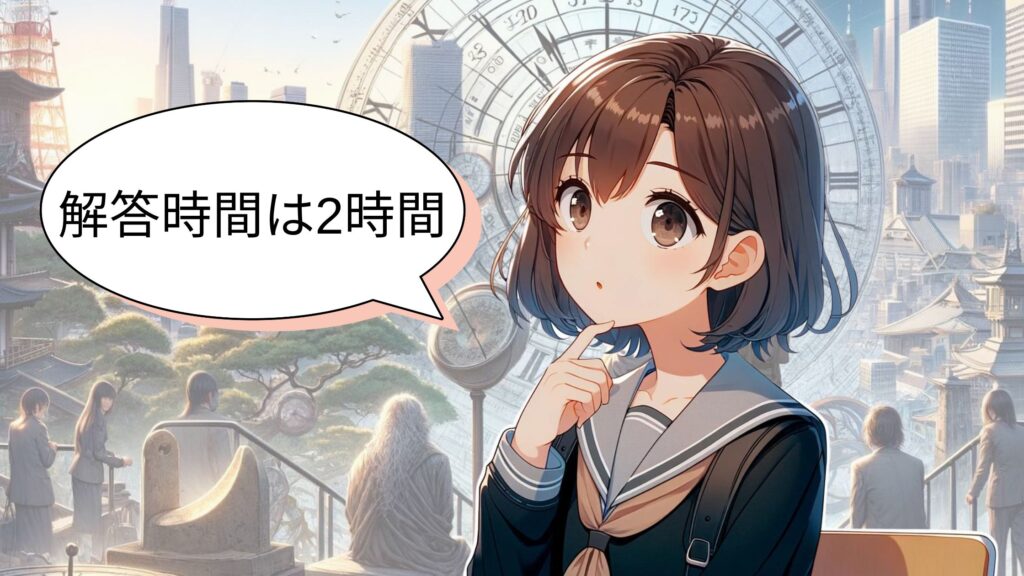
東京都特別区Ⅲ類の解答時間は2時間です。
2時間で45問なので、平均すると1問につき2分半ぐらいで解くことになります。
ただ、知能科目は1問解答するのに2分半以上かかってしまう問題もあります。
そのため、知識科目でいかに早く解答できるように勉強しておくかが大切。
東京都特別区Ⅲ類の知識科目は、他の公務員試験(国家一般職・地方初級・警察官など)の過去問で出題されたものと同じポイントがかなり出ています。
過去問を使った対策は必須です!
必須解答の問題と選択解答の問題がある


東京都特別区Ⅲ類の試験では、必須解答の問題と選択解答の問題があります。



選択解答があるのが、東京都特別区Ⅲ類の最大の特徴!
問題は全部で50問。50題中45題を解答します。
知能科目は28題必須解答、知識科目は22題中17題選択解答。
| 知能科目 (必須解答) | 出題は28題 | 28題全て解答 |
| 知識科目 (選択解答) | 出題は22題 | 22題中17題を解答 |
知識科目は、解答しなくもいい問題を5題選べます。



この5題をどう選択するかが、試験戦略として重要。
※要注意※17 問を超えて解答した場合は、解答数が 17 に達したところで採点を終了し、17 を超えた分については採点されません。
特別区人事委員会のホームページで、過去3年分の問題が公開されているので、これを見て自分なりの試験戦略を立てましょう。
解答は「公務員試験総合ガイド」のホームページに掲載されています。
なお、著作権の関係で文章理解の問題は掲載されていません。
東京都特別区Ⅲ類の文章理解の問題を見たい場合は、過去問350シリーズの地方初級に掲載されています。
現代文では主旨把握が出題される


例年の傾向では、東京都特別区Ⅲ類の現代文は6問出題されます。
現代文では、主旨把握、短文並べ替え、空所補充が各2問出されるのが例年の傾向。



主旨把握は慣れないと解きずらいので、過去問で練習しておくことをおススメします。
国家一般職や地方初級で多いのは「内容把握」。
「内容把握」と「主旨把握」は、問題の見た目は同じでも解き方が異なります。
「内容把握」は問題の最初に「次の内容と一致するものはどれか。」と書いてあります。
「主旨把握」は問題の最初に「次の文の主旨として、最も妥当なのはどれか。」と書いてあります。



地味だけど、この違いはとても大切!
「内容把握」の解き方で「主旨把握」を解こうとすると大失敗します。
東京都特別区Ⅲ類を受ける人は、過去問で「主旨把握」を必ず解いておきましょう。
知能科目の出題が多い
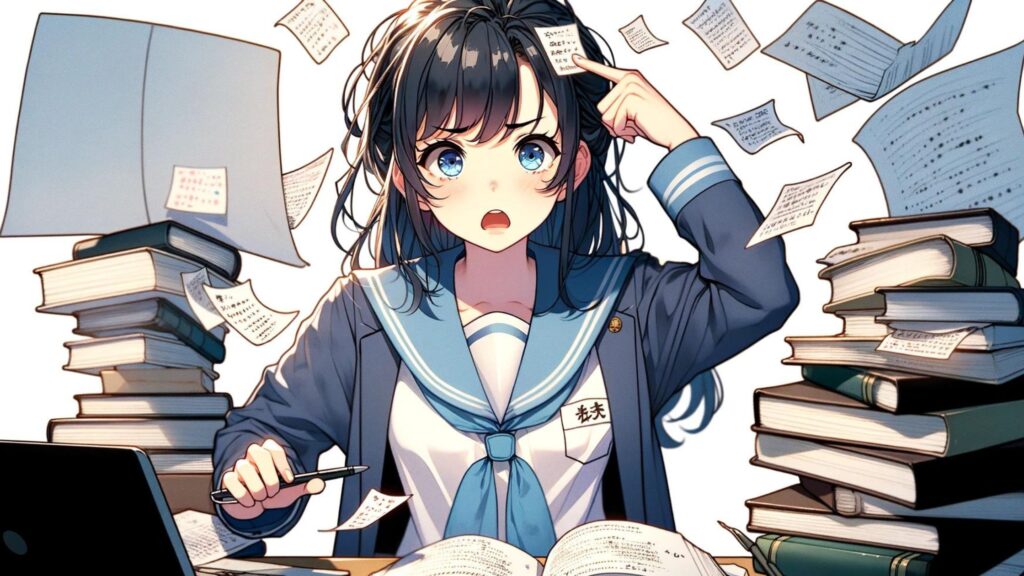
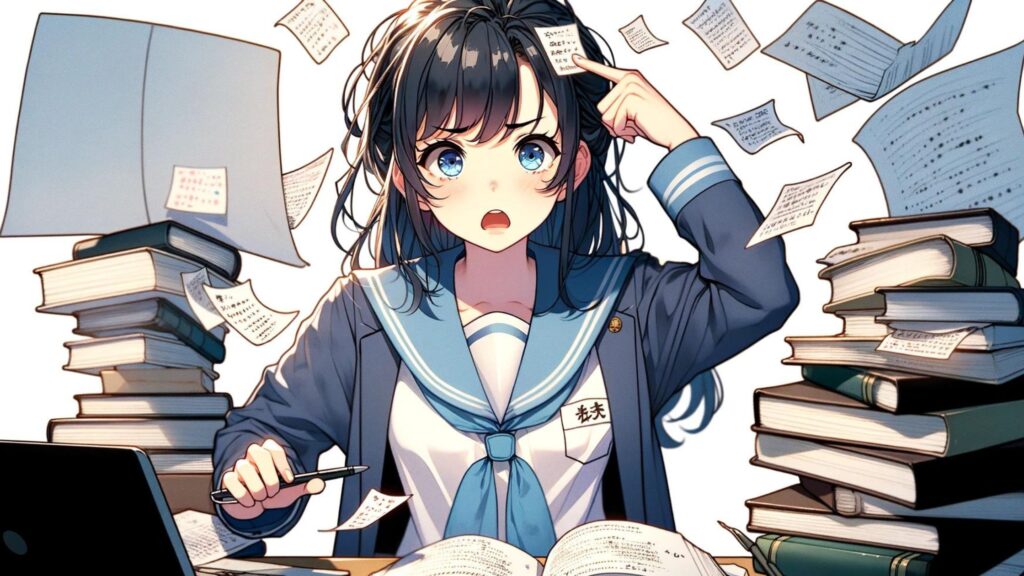
東京都特別区Ⅲ類では、知能科目は28題必須解答、知識科目は22題中17題選択解答。
問題の半分以上が知能科目です。



知能科目重視の傾向!
知能科目は、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈など。
判断推理、数的推理は特に力を入れて学習しましょう!
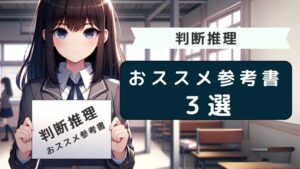
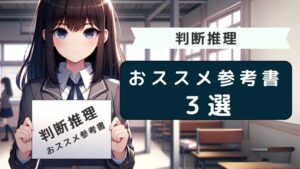
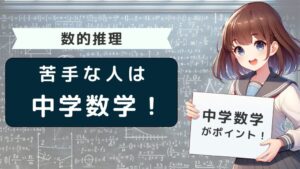
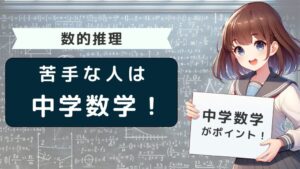
判断推理では暗号が出される
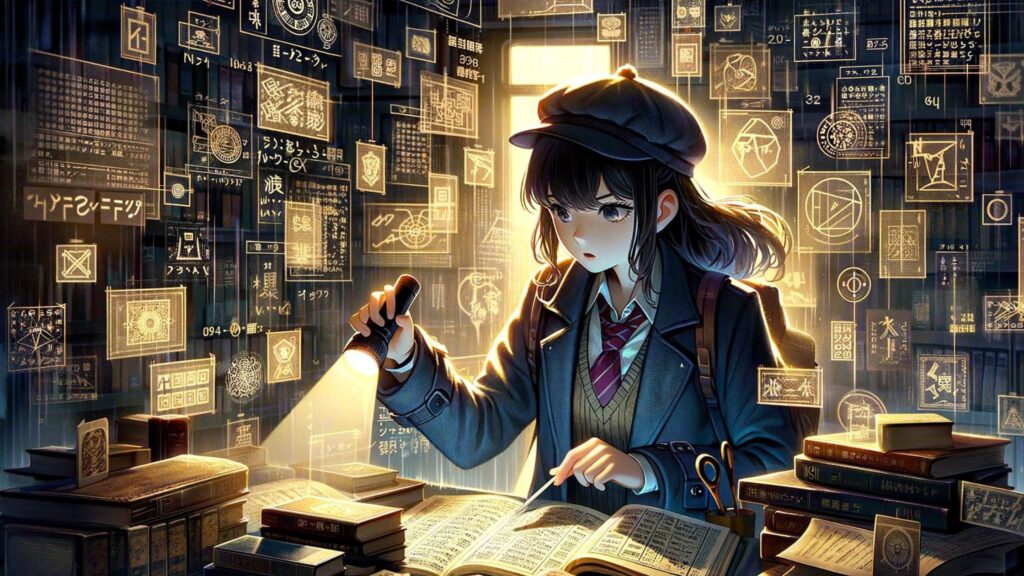
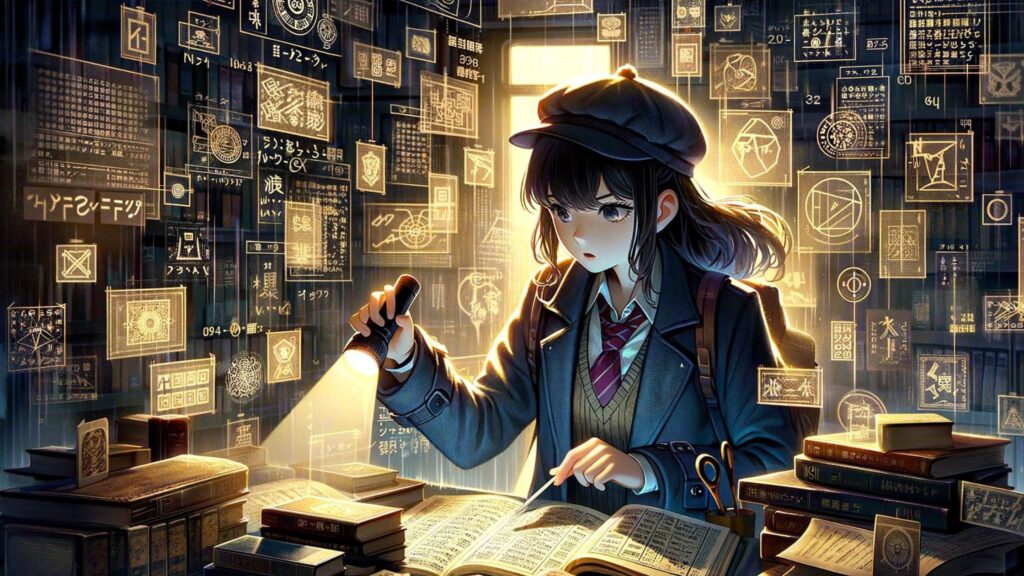
例年の傾向だと、判断推理では暗号が毎年出ています。



これは、東京都特別区Ⅲ類の独特の傾向。
他の高卒公務員試験では、暗号の出題頻度は低いです。
国家一般職や地方初級、警察官などを受ける人にとっては暗号の優先順位が低いですが、東京都特別区Ⅲ類を受ける方は優先度が高くなります。





東京都特別区Ⅲ類を受ける人は暗号の学習をしましょう!
資料解釈が4問出題される


東京都特別区Ⅲ類では、資料解釈が4問出題されます。
他の高卒公務員試験は、資料解釈の出題は2問がほとんど。
4問の出題はかなり大きいです。
しっかりと資料解釈の対策をして、点数を取れるようにしておくことが大切。
高卒公務員試験の資料解釈の勉強には、畑中先生のテキストがおススメです。
問題は持ち帰り可能


東京都特別区Ⅲ類では、問題用紙を持ち帰ることができます。
試験終了後、数日するとホームページで解答も発表されます。



自己採点が可能です!
自己採点をして、以降の試験に活かしましょう。
診断
あなたに最適な講座を診断
\簡単全3問/


あなたには「クレアール」ル警察官・消防官コースがおススメ
✅ 警察官・消防官コースがある
✅ 低価格で受講できる
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたにはアガルートがおススメ
✅ 低価格でさらに割引あり
✅ スキマ時間で効率的な学習が可能
✅ フォロー制度も充実
低価格で充実のフォロー制度!この価格で作文添削、模擬面接もあり!


あなたにはアガルートがおススメ
✅ 低価格でさらに割引あり
✅ スキマ時間で効率的な学習が可能
✅ フォロー制度も充実
低価格で充実のフォロー制度!この価格で作文添削、模擬面接もあり!


あなたには「クレアール」がおススメ
✅ 低価格で受講できる
✅ 「安心保証」で受講期間が1年間延長できます
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたには「クレアール」ル警察官・消防官コースがおススメ
✅ 警察官・消防官コースがある
✅ 低価格で受講できる
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたには「 資格スクール 大栄 」がおススメ
✅ 全国に直営校50拠点以上
✅ 「通学」・「オンライン」が選べる
✅ 二次試験対策がかなり充実してる
充実の二次対策!面接や作文が苦手な人には大栄がおススメ!


あなたには「クレアール」地方初級・国家高卒併願コースがおススメ
✅ 地方初級・国家高卒併願コースがある
✅ 低価格で受講できる
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたには「 資格スクール 大栄 」がおススメ
✅ 全国に直営校50拠点以上
✅ 「通学」・「オンライン」が選べる
✅ 二次試験対策がかなり充実してる
充実の二次対策!面接や作文が苦手な人には大栄がおススメ!
まとめ
- 解答時間は2時間。
- 必須解答の問題と選択解答の問題がある。
- 過去問3年分がホームページで公開されている。ただし、文章理解は公開されていない。
- 現代文では主旨把握が出題される。
- 判断推理では暗号が出題される。
- 資料解釈が4問出題される。
- 問題用紙は持ち帰り可能。