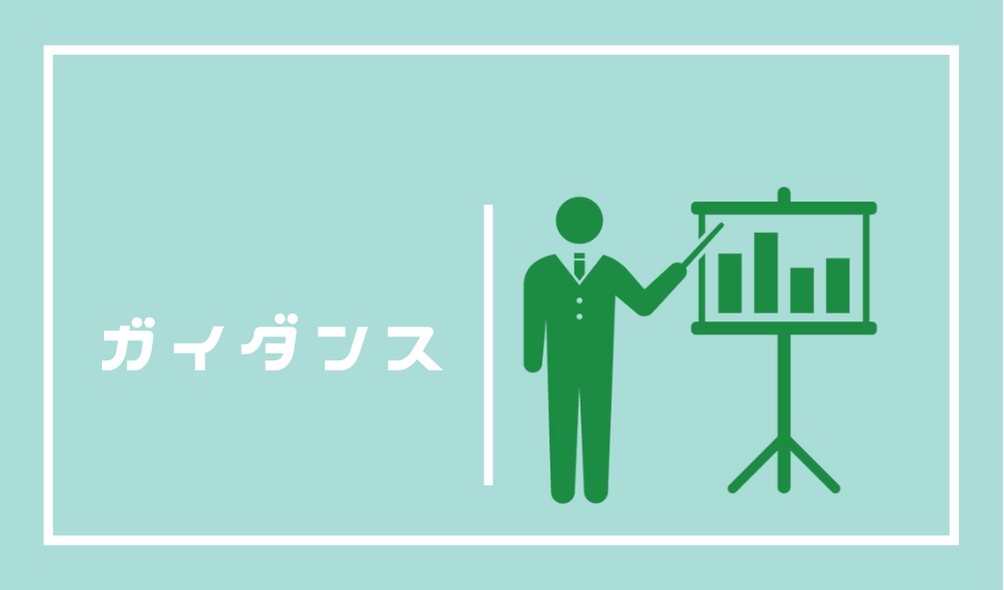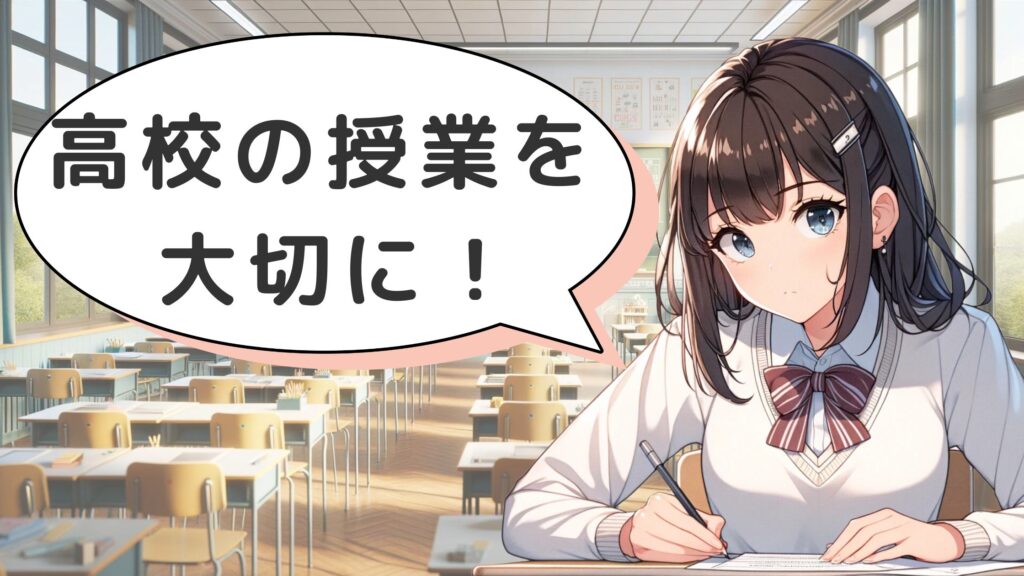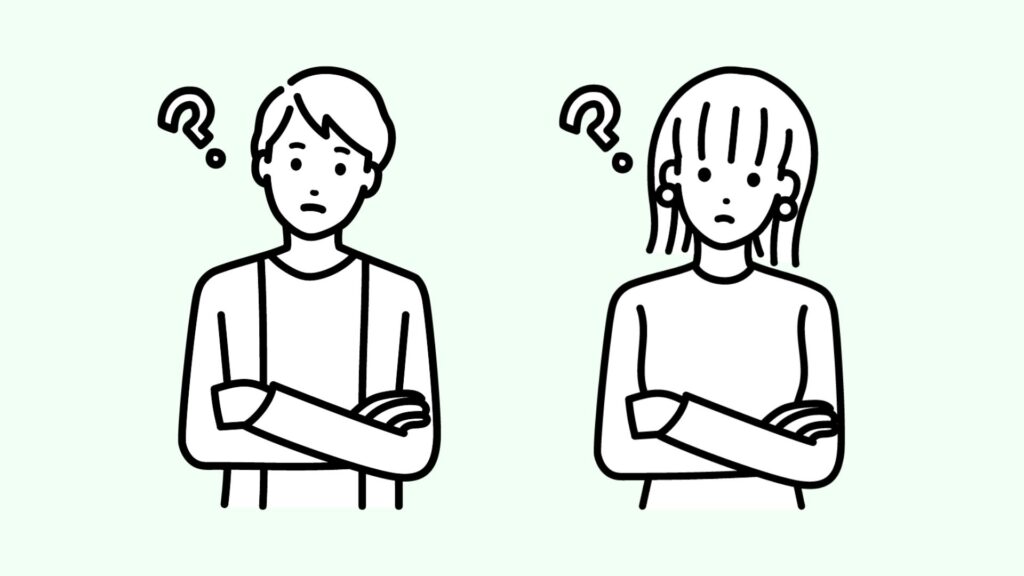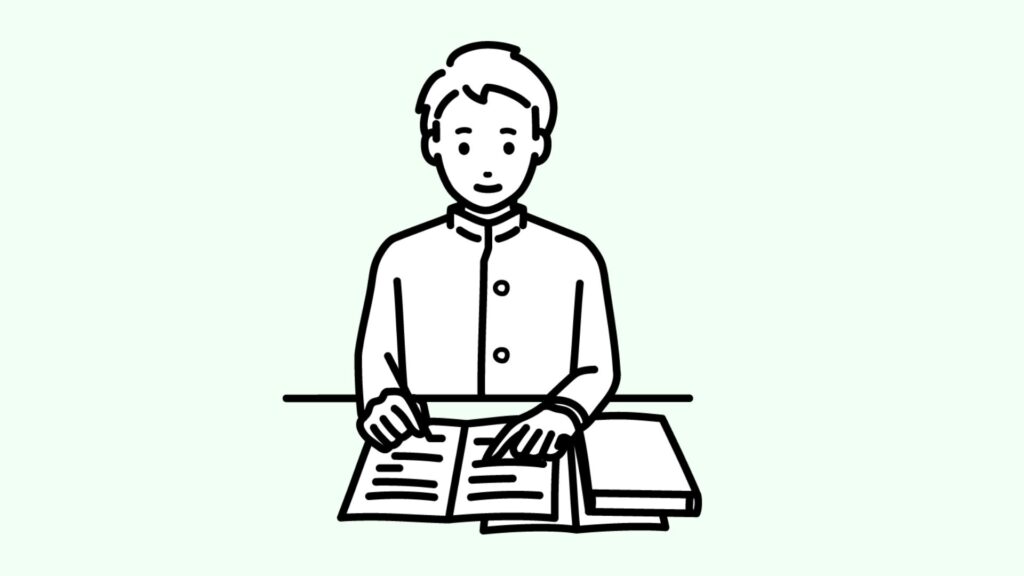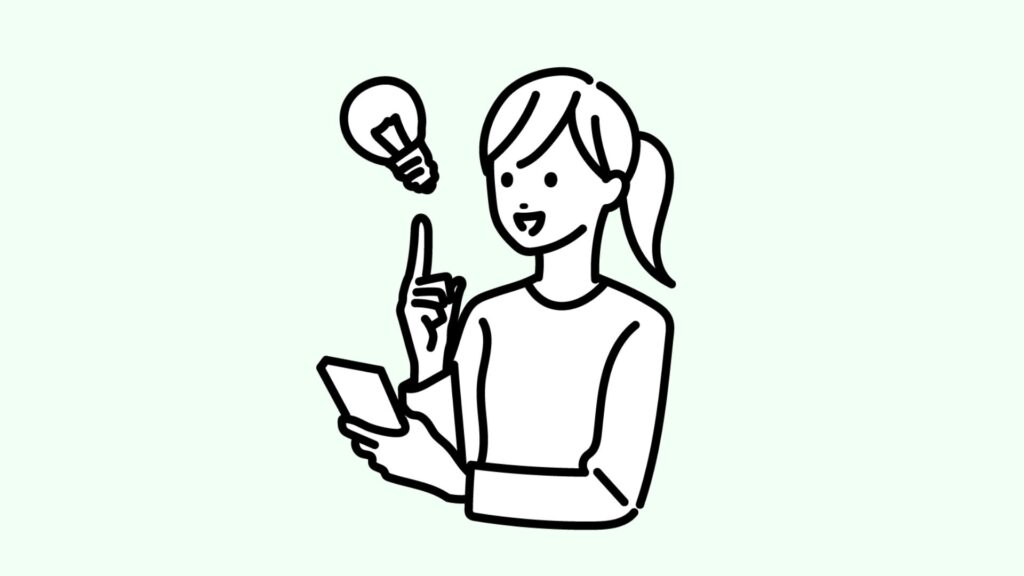高校生は毎日の授業があって、部活動やアルバイトもやっていると勉強時間が取れなくて大変。
『公務員試験の勉強をする時間が無いよ~』と悩んでいる高校生にアドバイスです。

高卒公務員に合格したいけど時間が無い高校生は、高校の授業を大切にしましょう!
- 公務員試験に合格したい高校生
- 部活やアルバイトで、勉強時間がなかなか取れない高校生
- 公務員試験の勉強の仕方で悩んでいる高校生
ここでは、なぜ高校の授業を大切にするのか、授業を公務員試験に活かすにはどうすればいいかを解説します。



高卒公務員指導歴10年以上、元・専門学校公務員科教員の僕が解説します!
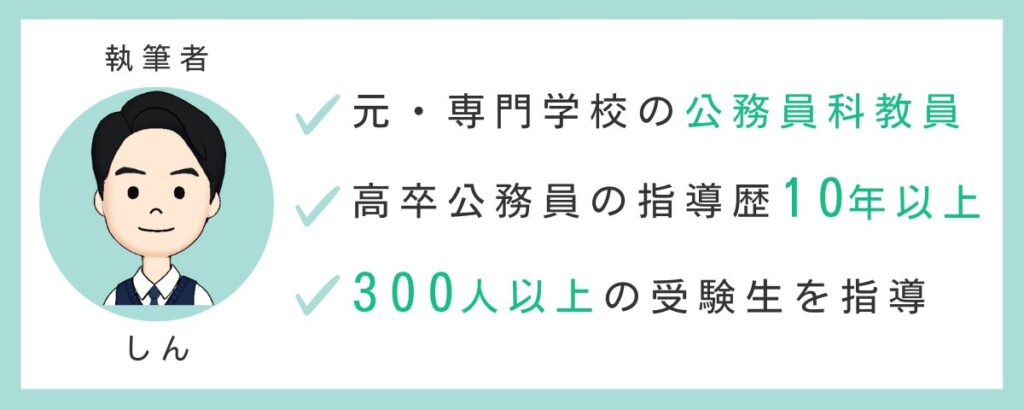
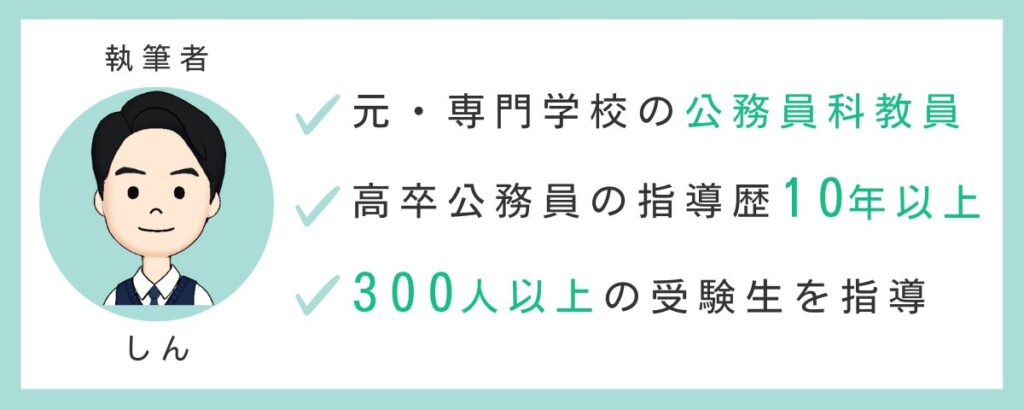
X(Twitter)しん@元・専門学校の公務員科教員
\ 高卒の対策講座があるのはこの9つ/
  |   |   |   | ||||||
| 価格 | 150,000円 | 約165,000円~ | 376,475円~ | 118,000円 | 84,000円~353,500円 | 148,000円 | 35,200円 | 199,600円 | 127,300円 |
| 割引 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 受講 | 通信 | 通学 | 通信・通学 | 通信 | 通信・通学 | 通信 | 通信 | 通信・通学 | 通信 |
| 警察官・消防官コース | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 作文対策 | 有 添削回数無制限 | 有 回数無制限 | 有 | 有 1人3通 | 有 | 有 添削3回 | 有 添削2回 | 有 | 有 添削1回 |
| 模擬面接 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 有 | 有 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 無 | 有 | 有 回数無制限 |
| 特徴 | 充実のカリキュラム!通信ならここがおススメ! | 担任の面倒見が良い予備校。高い合格率も魅力 | 二次試験対策にこだわったスクール | 価格で選ぶならアガルート。今なら10%OFF! | 大手ならではの情報量と分析で受験生をサポート | 万全の面接対策で独学では不可能な部分もカバー | 動画ではなく、テキストを自習するスタイル | 全国展開の専門学校で有名な大原グループが運営 | 無料で1年間の学習期間の延長サービスがある |
| 公式 サイト | クレアール | EYE | アガルート | 東京アカデミー | LEC
| 実務教育出版 | 資格の大原 | Human
| |
| 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求
| ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 |
高卒公務員の受験科目は、半分以上が高校までに習う内容
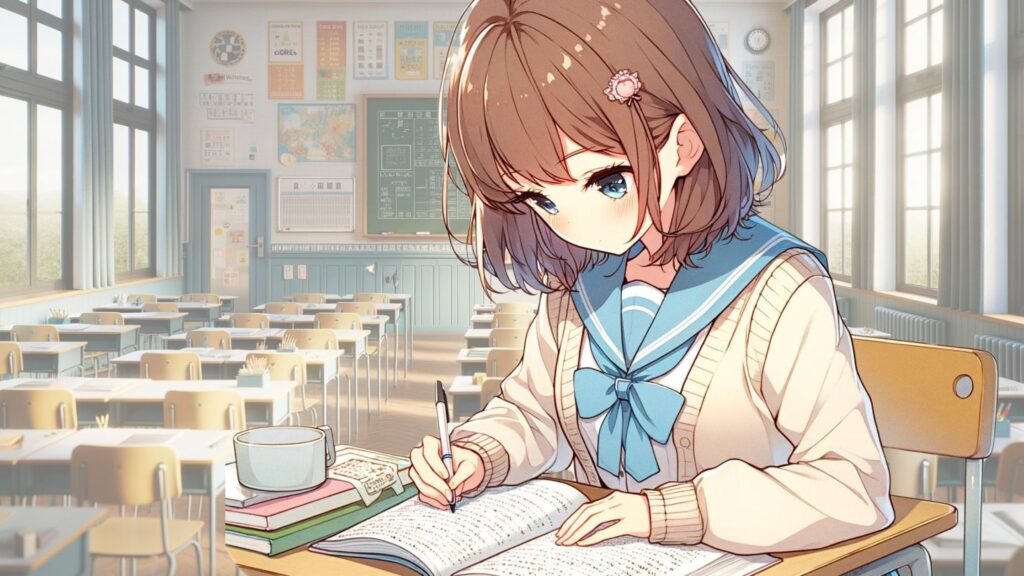
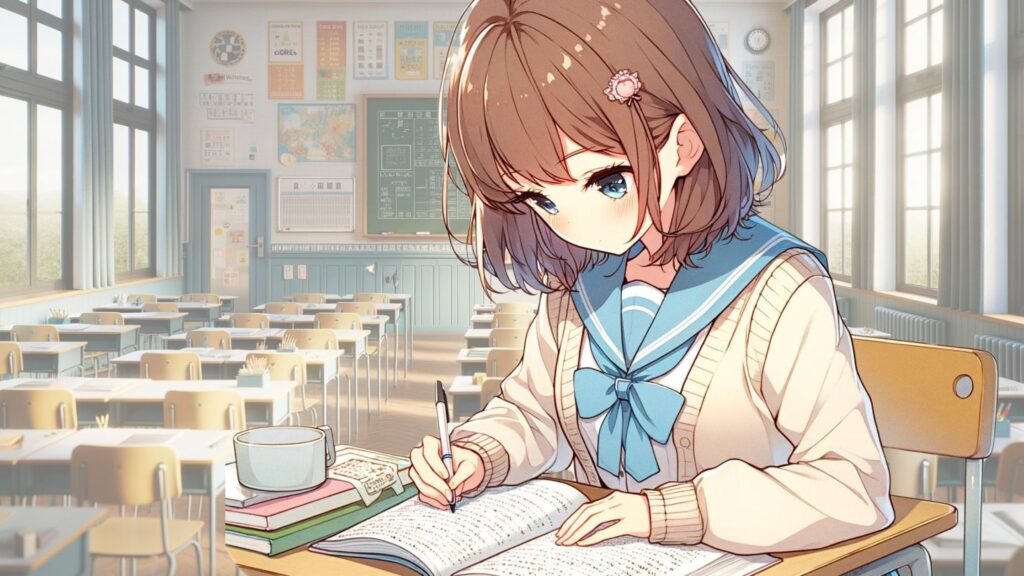
高卒公務員の受験科目は、半分以上が高校までに習う内容です。
出題科目はおおむね下の表のようなものです。
| 文章理解(現代文 英文) |
| 判断推理 |
| 数的推理 |
| 資料解釈 |
| 社会科学(政治、経済、社会) |
| 人文科学(日本史 世界史 地理 漢字 熟語) |
| 自然科学(数学 物理 化学 生物 地学) |



このような科目なので、高校の授業がそのまま試験対策になります
ただし、高校で習う内容でも、公務員試験に出題されやすいところ・出題されにくいところがあります。
そのため、出題傾向に応じた対策が必要になります。
例えば、高卒公務員試験の世界史だと中国史が出題されやすかったりします。
授業を高卒公務員試験に活かすには?


高卒公務員試験には出題傾向があるため、それを把握したうえで授業を受けると、効率よく学習できます。



具体的にはどうすればいいんですか?



予習・授業中・復習と、次のようにやると効果的です。
出題傾向を把握するには、過去問を解くのが一番です。
過去問を解いてみると、高校の授業の中でも「ここは出やすいな!」「ここまでは出ないな」というのが分かってきます。
ですので、過去問を解いてください!
っといっても、いきなり過去問を解くのは難しいですよね。
まずは予習として、次の授業で習うところの過去問にざっと目を通してください。
じっくり解く必要はないです。どんな感じで出題されているのか?が把握できれば大丈夫です。



授業で習ったら、その範囲の過去問にチャレンジしてみてください。
例えば、政治経済の授業で「需要・供給」を習ったら、過去問からその分野を探して解くという方法です。
このように学習することで、公務員試験に向けて効果的に授業を受けることができます。
過去問は実務教育出版の過去問350シリーズがおススメ。



どれを買えばいいかわからないんですけど・・・



志望先に対応するのを買えば大丈夫です。
国家一般職と税務職員は同じ問題が出題されます。
税務職員を志望する人は、「国家一般職」を選んでください。
「地方初級」は市役所の職員、都道府県職員を志望する人向けです。



まだ志望先が決まってないんです。



その場合は、「高卒警察官350」を買いましょう。



私、事務職が希望で警察官は全く考えてないんですけど・・・



まずは「高卒警察官350」で基礎固めをして、2冊目で「国家一般職350」か「地方初級350」を買って実力アップをするのがいいんです!
高卒公務員試験の場合、警察官、国家一般職、地方初級で出題されるポイントは同じです。
ただ、問題の難易度は異なります。
国家一般職、地方初級 に比べて警察官の過去問はやや易しいです。
易しめの 「高卒警察官350」 から「 国家一般職」「地方初級」へ ステップアップしてとスムーズに学習できます。
- 志望先が決まっていない人。
- 志望先は「国家一般職」「地方初級」に決まっているけど勉強に自信が無い人
診断
あなたに最適な講座を診断
\簡単全3問/


あなたには「クレアール」ル警察官・消防官コースがおススメ
✅ 警察官・消防官コースがある
✅ 低価格で受講できる
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたにはアガルートがおススメ
✅ 低価格でさらに割引あり
✅ スキマ時間で効率的な学習が可能
✅ フォロー制度も充実
低価格で充実のフォロー制度!この価格で作文添削、模擬面接もあり!


あなたにはアガルートがおススメ
✅ 低価格でさらに割引あり
✅ スキマ時間で効率的な学習が可能
✅ フォロー制度も充実
低価格で充実のフォロー制度!この価格で作文添削、模擬面接もあり!


あなたには「クレアール」がおススメ
✅ 低価格で受講できる
✅ 「安心保証」で受講期間が1年間延長できます
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたには「クレアール」ル警察官・消防官コースがおススメ
✅ 警察官・消防官コースがある
✅ 低価格で受講できる
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたには「 資格スクール 大栄 」がおススメ
✅ 全国に直営校50拠点以上
✅ 「通学」・「オンライン」が選べる
✅ 二次試験対策がかなり充実してる
充実の二次対策!面接や作文が苦手な人には大栄がおススメ!


あなたには「クレアール」地方初級・国家高卒併願コースがおススメ
✅ 地方初級・国家高卒併願コースがある
✅ 低価格で受講できる
✅ 模試・面接対策も講座に含まれている
面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座
クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト


あなたには「 資格スクール 大栄 」がおススメ
✅ 全国に直営校50拠点以上
✅ 「通学」・「オンライン」が選べる
✅ 二次試験対策がかなり充実してる
充実の二次対策!面接や作文が苦手な人には大栄がおススメ!
まとめ
- 資高卒公務員の受験科目は、半分以上が高校までに習う内容。
- 高校で習う内容でも、公務員試験に出題されやすいところ・出題されにくいところがある。
- 出題傾向を把握したうえで授業を受けると、効率よく学習できる。
- 出題傾向を把握するには、過去問を解くのが一番。
- 過去問は実務教育出版の過去問350シリーズがおススメ。